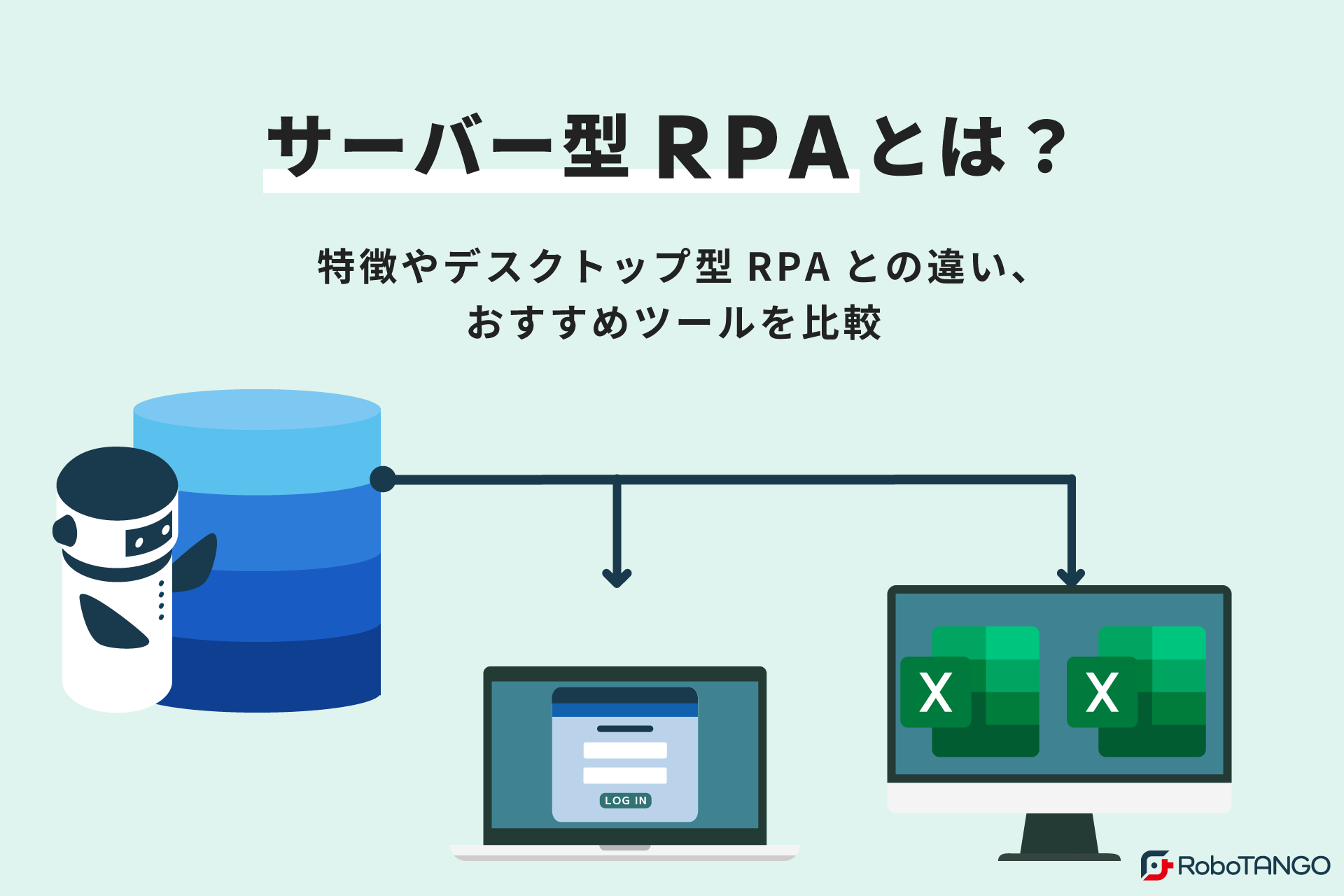押さえておくべきRPAソフトウェアの3つの選定基準

RPAソフト選定基準①実行環境【スタンドアロン型とサーバーコントローラー型の比較】
まず1つの目のRPAソフト選定基準は実行環境です。
スタンドアロン型はRPAソフトをPCにインストールし、デスクトップ上で動作します。シナリオを人間のオペレーションで起動し、シナリオ実行中にファイル選択や指定といったかたちで人間の判断を介在させることも可能です。RPAソフトを用いて半自動のロボを作成したいという際にも活用できます。一部フリーウエアの無料ツールもあります。
サーバーコントローラー型はサーバー上でロボを設定し、サーバーからの命令でRPAソフトがPCを操作します。複数台のPCでのRPAソフトの稼働を一元管理でき、大規模な完全自動化に向いています。RPAソフトは海外メーカー製が多く、導入事例としても、日本でも大企業が多く活用しているツールです。
RPAソフト選定基準②ロボ開発手段【GUI型とコーディング型の比較】
2つの目のRPAソフト選定基準はロボ開発手段です。GUI型がコード入力を必要としない開発方法で、プログラミング未経験の人でもRPAロボを開発できるものです。コーディング型はコードを書いてRPAロボの動作を設定するもので、プログラミング言語の知識が必要とされます。
RPAソフト選定基準③導入形式【オンプレミス型とクラウド型の比較】
2つの目のRPAソフト選定基準は導入形式です。オンプレミス型RPAは自社内のサーバーやPCにRPAソフトをインストールするツールです。自社内の他のシステムと連携することもできます。一方クラウド型RPAはクラウド環境にRPAソフトのロボを導入するものです。Webブラウザ上での作業を自動化でき、比較的安価で導入できる点が特徴です。
ソフトによって対応アプリケーションは異なる
ソフトには様々な種類があります。ソフトごとに対応するアプリケーションもことなりますので、社内で使用しているツールとの互換性についても確認し、導入を検討すべきです。
導入規模で選ぶときは実行環境をチェック
ここからは導入規模でRPAソフトを選ぶ時のポイントについて説明します。
スタンドアロン型RPAは小規模導入向き
スタンドアロン型のRPAソフトは低価格かつ専門知識がない人でも取り扱えるものが多いため、小規模導入にむいています。具体的には、WinActorとロボパットがおすすめです。理由は直感的な操作でRPAロボに操作設定ができることと、柔軟に業務手順を設定できるためです。WinActorはNTTによって開発されたバックボーンがあり、無料セミナーを開催するなど、積極的にシェアを拡大しています。いずれのRPAソフトも、導入企業一覧には2019年時点で様々な企業が名を連ねています。
サーバーコントローラー型RPAは全社展開を見据えて
サーバーコントローラー型RPAソフトの魅力はRPAロボをサーバーで一括管理できることです。複数部署でRPAソフトを導入し業務改善したい企業にとって、運用・連携がしやすいでしょう。サーバーコントローラー型RPAソフトのおすすめには、BizRobo!とBluePrismがあります。
BizRobo!は国内1000社の導入実績を持つRPAソフトで、「ITreview Grid Award 2020 Summer」の「RPA部門」で最高位を獲得した実績があります。BluePrismはイギリス製のRPAソフトで、セキュリティ面や会計業務に強みを持っています。海外のメガバンクやSiemensをはじめ、世界各国の企業に導入されています。日本語にも対応し、使い方や意味がわからないという事態になることはないでしょう。
ロボ化の自由度で選ぶときはロボ開発手段をチェック
次には開発手段でRPAソフトを選ぶ時のポイントについて説明します。
GUI型RPAは開発が容易
操作を記憶させることでRPAソフトを開発できるGUI型は、コーディングの知識やスキルと必要としないためコストを抑えてRPAツールを導入することができます。WinActorやUiPathがGUI型のおすすめで、開発の容易さから多くの企業に導入されています。
コーディング型RPAは複雑な作業も自動化できる
コーディング型はその名の通りコードを入力し、RPAソフトを開発していくため、プログラミング言語を使えることが条件となります。おすすめのRPAソフトとしてはUWSCやSikuliなどがあります。RPAソフトの導入に対して、画像認識といったより高度なソリューションを求める際にはコーディング型が活用されます。
自社での保有可否で選ぶときは導入形式をチェック
最後に導入形式でRPAソフトを選ぶ時のポイントについて説明します。
オンプレミス型RPAは自社独自のソフトもロボ化しやすい
オンプレミス型のRPAソフトは自社内のソフトとひもづけて運用できる点が特徴です。RPAソフトと連携させたいソフトが多い場合にはオンプレミス型が選ばれています。おすすめのRPAソフトとしては米国で大きなシェアを持つAutomation Anywhereや柔軟にRPAロボを開発できるUiPathなどがあげられます。いずれのRPAロボも自社独自のソフトとの連動に強みを持ち、多くの企業の業務効率化をサポートしています。
クラウド型RPAは短期間で導入できる
クラウド型のRPAソフトはクラウド上での動作を自動化する際に強みを発揮します。おすすめのRPAソフトとしてはBizteX cobitやRobotic CrowdやWorkFusion Studioなどがあります。BizteX cobitは、国内初のクラウド型RPAとして低価格で始めやすいクラウド型RPAとなっています。Robotic CrowdのRPAの特徴はソフトインストールや環境構築が不要で、自動バージョンアップと、手間がかからない点です。また、WorkFusion StudioのRPAは無料で使える高機能なフリーソフトとして有名で、多くの企業に活用されています。
RPAソフトを導入したいが、ツール価格が気になるという場合は、無料のWorkFusion Studioから活用をはじめる方法もあります。フリーの無料ソフトですので、個人利用もできるでしょう。
RPAソフト選定のまとめ
RPAソフトは多くの企業にとって様々な業務の助けとなるツールです。近年ではOSS(オープンソースソフトウェア)のRPAツールやRPM・RPSといった対応業務に特化したRPAツールも増えてきています。さらに、RPA Expressのように、無料版ツールのStarterと有料版ツールのProという形でタイプを選んでRPAツールを導入できる製品もあります。
フリーのRPAツールも増えつつあるなかで、2018年には日本で初めてのRPA関連資格「RPA技術者検定」がスタート。RPAソフトの導入・運用にはRPAツールの専門知識が必要だと認識されるようになりました。これからRPAソフトを導入する際には様々なツールを比較検討し、自社に最適なツールを選択したいものです。